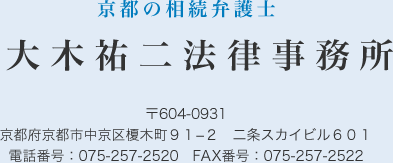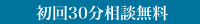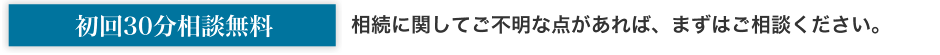相続コラム
配偶者居住権の意義とその内容について
第1 はじめに
第2 配偶者居住権について
第3 配偶者短期居住権について
第4 配偶者居住権のメリットとデメリット
第5 配偶者の居住権を確保するための民法上の他の方策について
第6 終わりに
第1 はじめに
配偶者居住権とは、大まかにいえば、被相続人の死後も、その配偶者が、被相続人所有の居住建物に住み続けられる制度です。
制度目的は、被相続人の死後、残された配偶者が住み慣れた家に住み続けられるよう居住権を保護することで、配偶者の精神的・肉体的な負担を軽減し、もって生活保障を図ることです。
この記事では、配偶者居住権について、配偶者短期居住権と比較しながらそれぞれが成立する要件および効果、メリットとデメリット、他の制度との関連について説明します。
第2 配偶者居住権について
1 要件
配偶者居住権が成立するための要件は、民法1028条1項によると以下の3つになります。
⑴ 配偶者が、相続開始時に、遺産である建物に居住していたこと
ここでいう「配偶者」とは法律上、被相続人と婚姻関係にあった配偶者を意味します。内縁の配偶者、事実婚関係や同性婚のパートナーには認められません。
また、「居住していた」とは、配偶者が配偶者居住権の対象となる建物を生活の本拠にしていたことを意味します。したがって、例えば、被相続人が所有する別荘や、すでに被相続人が老人ホームに入居済みであるときの住居などは、対象外です。一方、被相続人の配偶者が、療養を目的とする一時的な入院をしていた場合において、配偶者の家財や家具がその建物に存在しており、退院後にそこに帰ることが予定されていた場合、実質的には未だ被相続人が相続対象となる建物に「居住していた」とされます。さらに、季節ごとに異なる建物で生活していた場合は、複数の建物について配偶者居住権が成立する可能性もあります。
⑵ 建物が被相続人の単独所有であること、あるいは、被相続人と配偶者と二人の共有にかかるものであること
被相続人が居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合、配偶者居住権は成立しません(1028条1項ただし書)。これは、配偶者居住権が設定されることにより、他の共有持分権者が第三者に無償で居住建物の使用を受忍するという過大な負担を負わせることになるからです。
⑶ 配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈、死因贈与がされたこと
遺産分割には、協議による分割、調停による分割、審判による分割が含まれます。
遺贈には、特定財産承継遺言(いわゆる「相続させる旨の遺言」)は含まれません。もっとも、特定財産承継遺言において、遺産全部の帰属が定められ、その中で、配偶者に配偶者居住権を相続させる旨の記載があった場合、遺贈の趣旨であると判断されることがあります。
2 効果
配偶者居住権の効力は、次の2点があげられます。
⑴ 建物の使用及び収益をする権利
配偶者は、配偶者居住権に基づき、建物を無償で使用及び収益することができます。ただし、建物を増改築し又は第三者に建物を使用若しくは収益させるときは、建物所有者の承諾が必要となります(民法1032条3項)。
また、配偶者は、居住建物の「通常の必要費」を負担します(民法1034条1項)。ここには、居住建物の保存に必要な修繕費、居住建物とその敷地の固定資産税も含まれると考えられています 。
⑵ 譲渡禁止
配偶者居住権は、他人に譲渡することができません(民法1032条2項)。譲渡を認めてしまうと、配偶者の従前の居住環境を確保する、という制度趣旨にそぐわないからです。
3 存続期間
配偶者居住権の存続期間の定めがないときは、その期間は配偶者の終身の間とされます(民法1030条前段)。ただし、遺産分割協議や調停、遺言によって終身とは異なる存続期間を定めることも可能です(民法1030条後段)。存続期間が定められた場合、適切な財産的価値の評価を行うため、その延長や更新はできないとされています 。
4 消滅事由と消滅後の法律関係
配偶者居住権は、以下の場合に消滅します(前掲東京家庭裁判所家事第5部 66頁)。
- ⑴配偶者が死亡した場合(民法1036条・597条3項)
- ⑵存続期間が終了した場合(民法1036条・597条1項)
- ⑶居住建物が全部滅失等した場合(民法1036条・616条の2)
- ⑷居住建物の所有者による消滅請求がなされた場合(民法1032条4項)
- ⑸居住建物が配偶者の単独所有となった場合(混同による消滅。民法1028条2項)
- ⑹配偶者が配偶者居住権を放棄した場合(債権放棄による消滅)
配偶者居住権が消滅した場合、配偶者は居住建物の所有者に対して、居住建物を返還
する必要があります(民法1035条1項)。ただし、配偶者が居住建物の共有持分を有している場合には、配偶者居住権の消滅を理由として、所有者から返還請求を受けることはありません(同条1項ただし書)。
第3 配偶者短期居住権について
配偶者短期居住権は、相続開始後から比較的短期間の居住権を保護するための制度です。配偶者居住権とは異なり、特別な手続きを経ずとも認められることが特徴として挙げられます。
1 要件
(1) 配偶者が、相続開始時に、遺産である建物に無償で居住していたこと
「配偶者」とは、法律婚をしていた配偶者を指します。もっとも、法律婚配偶者であっても①配偶者居住権を取得した配偶者②相続欠格・廃除を受けた配偶者③相続開始時に単独で居住建物の所有権を取得した配偶者④相続放棄をした配偶者のいずれかに該当する場合は、配偶者短期居住権を取得することができません。
「居住していた」とは基本的には配偶者居住権と同様、生活の本拠としていることが必要です。
また、「無償」で居住していたことも重要な要件です。
(2) 建物が被相続人の財産に属したものであること
相続開始時点で、被相続人が居住建物を所有していたことが必要です。これには、単独所有のみならず、共有持分を有していた場合も含まれます。ただし、被相続人が第三者と建物を共有していた場合は、他の共有者に対して当然に配偶者短期居住権を主張できるわけではなく、被相続人と他の共有者の間の約定に基づき主張の可否が決せられます。
2 効果
(1) 居住建物の使用
配偶者居住権とは異なり、配偶者短期居住権によって配偶者が取得する権利は、使用権限のみで、収益権限は含みません。
また、配偶者居住権と異なる点として、相続開始時点において無償で使用していた部分が当該「建物の一部」に留まる場合は、その部分に限り使用する権限を有します。
(2) 無償での使用
配偶者短期居住権は使用対価を居住建物の所有者に対して支払う必要がありません。また、配偶者短期居住権に基づく使用利益は、遺産分割においても控除されません。
(3) 譲渡禁止
先ほど説明した配偶者居住権と同様、配偶者短期居住権も譲渡ができません。
3 存続期間
以下の場合に応じて存続期間が異なります。
(1) 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合(1037条1項1号)
この場合は、①遺産分割により居住建物の帰属が確定した日、又は②相続開始の時から6か月を経過する日のうち遅い日が終期となります。
(2) 配偶者が居住建物についての遺産分割に関与しない場合(1037条1項2号)
この場合は居住建物取得者から配偶者短期居住権の消滅の申入れ(1037条3項)がなされてから、6か月を経過する日が終期となります。
4 消滅事由と消滅後の法律関係
消滅事由は以下の6つです。
- ⑴存続期間が満了した場合(1037条1項)
- ⑵居住建物取得者による消滅請求を受けた場合(1038条3項)
- ⑶配偶者が配偶者居住権を取得した場合(1039条)
- ⑷配偶者が死亡した場合(1041条・597条3項)
- ⑸居住建物の全部滅失等により使用をすることができなくなった場合(1041条・616条の2)
- ⑹権利の放棄をした場合(519条)
配偶者短期居住権消滅後、配偶者は、原則、居住建物取得者に当該建物を返還する義務を負います。ただし、配偶者居住権を取得した場合や、配偶者が居住建物について共有持分を有するときは返還義務を負いません。
さらに、相続開始後に居住建物に附属させたものについて収去する義務や、相続開始後に生じた損傷について原状回復義務を負います。
配偶者居住権と配偶者短期居住権の相違点について、まとめると以下の表のとおりになります。
| – | 配偶者短期居住権 | 配偶者居住権 |
| 要件 | 特別の手続なしに権利を取得することができる。 | 遺産分割による取得など一定の手続が必要である。 |
| 効果 | 居住建物の使用 | 居住建物の使用と収益 |
| 範囲 | 相続開始時に使用していた範囲において、成立する。 | 居住建物全部について成立する。 |
| 終期 | 一定期間 | 原則、終身の間 |
| 登記 | できない | できる |
| 第三者対抗力 | なし | 登記をすれば対抗できる |
第4 配偶者居住権のメリットとデメリット
次に、配偶者居住権を設定するメリットとデメリットについて簡単に紹介します。
1 メリット
配偶者居住権の大きなメリットは、配偶者が長年居住してきた建物に住み続けることが可能となる点にあります。また、建物所有権の評価額よりも、配偶者居住権の評価額の方が低額の評価となります。その結果、遺産分割により、配偶者は建物の居住権に加え、他の財産、例えば預貯金や有価証券も相続することができるようになり、配偶者の生活全般を保障するような財産の相続が可能となります。
また、被相続人としても、自らの死後の配偶者の居住を確保しつつ、配偶者の死後は自らの子が建物を相続できるようにしたいといった構成を実現できるようになりました。
2 デメリット
一方、配偶者居住権のデメリットとしては、配偶者が建物を使用するにあたり、制限がかけられてしまうことがあります。例えば、先述した配偶者の建物の使用収益の制限や譲渡禁止があげられます。また、「通常の必要費」、すなわち、固定資産税や建物の保存に必要な修繕費についても配偶者が負担する必要があります。配偶者は何ら財産的な負担なしに建物に居住できるわけではない点に、注意が必要です。
さらに、建物の配偶者居住権負担付所有権を有する配偶者以外の相続人にとっては、その売却が極めて困難であるという大きなデメリットがあります。そもそも「他人が現在住んでいる建物を購入する」という心理的障壁も存在します。これらの結果、建物を売却したいのに買い手が見つからない可能性があります。
実務では、配偶者、被相続人、配偶者以外の相続人、それぞれの視点からメリットとデメリットを考慮した上、配偶者居住権の設定を検討していきます。
第5 配偶者の居住権を確保するための民法上の他の方策について
配偶者の居住権を確保する方法としては、配偶者居住権の設定以外にも、以下の方法があります。
- ⑴遺産分割により、配偶者に居住建物の所有権を取得させたうえで、リバースモーゲージを利用する方法
- ⑵遺産分割後に、建物取得者との間で賃貸借契約、使用貸借契約を締結する方法
- ⑶遺産分割の際に、居住建物を配偶者と他の相続人の共有とする方法
- ⑷配偶者の生存中における遺産分割を行わず、配偶者死亡後にまとめて遺産分割をする方法
もっとも、いずれの方法によっても、相続人間の合意が必要となるため、相続人間で争いがある際には、合意を得ることが難しい場合も少なくないでしょう。
なお、リバースモーゲージとは、自宅不動産に担保権を設定して、金融機関等と締結した金銭消費貸借契約に基づき、毎月の生活資金を借り受け、借受人が死亡した場合には担保に入れていた自宅を処分して返済するという融資形態のことをいいます。都道府県の社会福祉協議会や住宅金融支援機構、民間の金融機関等がそれぞれ取り扱っています。詳細は各機関の紹介をご覧ください。
リバースモーゲージのメリットは、老後生活中、毎月の返済は利息のみであることや、自宅に住み続けながら老後の資金を確保できることがあげられます。
一方、デメリットとして、そもそも建物の価値が生活資金の担保として十分な価値を有していることが必要な点で一定のハードルがある点が挙げられます。さらに、老後生活が長期化することで、生存中に借入金額が貸付限度額に達してしまい建物が売却されるリスクや、不動産価格の下落により融資が打ち切られてしまうリスクもあります。
第6 終わりに
このコラムでは、配偶者居住権について、配偶者短期居住権の制度と比較しながら、その成立する要件や効果、メリットとデメリット、他の制度との関連について紹介しました。配偶者居住権は、遺言や遺産分割協議によって設定される必要がある権利です。権利の取得や財産評価にあたっては専門知識が求められる場面もあり、また、遺産分割手続全般に大きな影響を与えることもあります。
配偶者居住権の利用を検討されている方は、弁護士をはじめとする法律専門家に相談することをおすすめします。