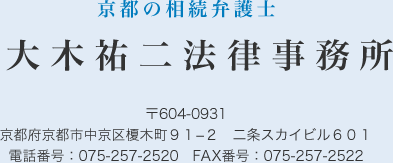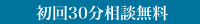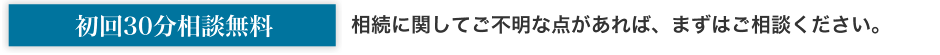相続コラム
不在者がいる場合の遺産分割
1 はじめに
遺産分割を進めようとした際に、自身の戸籍を遡ると自分の知らない人が相続人になっていることが分かったり、数年前から兄弟姉妹が行方不明になっていたりすることが多々あります。遺産分割協議には相続人全員の同意が必要であるため、不在者(行方不明の人)がいると相続人全員の同意が得られなくなってしまいます。今回は、「不在者がいる場合の遺産分割」についてお話いたします。
2 不在者の財産管理人選任
⑴ 前提
相続人の生存が明白であることが選任の前提条件です。その上で、相続人が行方不明で、様々な手段を用いたがその住所が判明しない場合、不在者の財産管理人を選任することを検討しましょう。その財産管理人が相続人と一緒に遺産分割協議を進めていきます。
⑵ 選任の手続
まずは不在者の従来の住所地または居住地を管轄する家庭裁判所に対し、不在者の財産管理人選任審判の申立てを行います。しかし、そもそも不在者であるため、住所地や最後の住所地、居住地が全くわからない場合もあります。その場合は、最後の住所地を基準にすることになりますが、それも不明である場合には、東京家庭裁判所か財産の所在地の家庭裁判所が管轄となります。
⑶ 財産管理人を交えた遺産分割の方法
遺産分割協議は、通常の財産管理人の権限の範囲を超えています。そのため、遺産分割協議前に、財産管理人は、不在者財産管理人の権限外行為許可審判の申立てを行い、協議事項につき事前の許可を得なければなりません。その上で、不在者に代わって不在者財産管理人が、不在者管理管理人として署名し、不在者管理管理人の実印を押印して遺産分割協議書を作成します。
3 失踪宣告
⑴ 前提
相続人の生存が明白であった不在者の財産管理人選任の場合と異なり、不在者の生死が不明である場合、失踪宣告の申立てを検討します。
⑵ 手続
不在者の住所地の家庭裁判所に対して申立てを行います。戦地に行ったなどの危難失踪もありますが、普通失踪(7年間生死が不明である場合)の場合が多いです。
⑶ その後の遺産分割の方法
失踪宣告の結果、失踪宣告を受けた不在者は死亡したものとみなされます。失踪者に相続人がいることが明白である場合、その相続人が遺産分割の当事者となります。一方、失踪者に相続人がいることが不明である場合、家庭裁判所による選任手続を経て、相続財産管理人が遺産分割の当事者となります。
4 まとめ
不在者がいるのに、それを無視して遺産分割協議を行った結果、不動産登記の移転や銀行での手続きができない事態に陥ることもあり得ます。そうならないよう、不在者についてもきちんと法的手続きを踏んで、円滑に遺産分割を進めていきましょう。