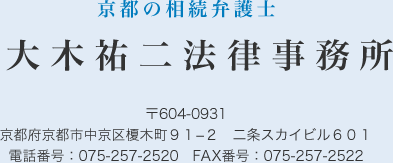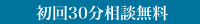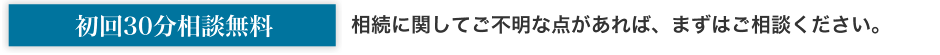相続コラム
法定相続分について
1 はじめに
被相続人が亡くなって相続人が複数いる場合は,誰が何をどのくらい取得するのかを決めていかなくてはなりません。相続人の間で問題なく遺産分割ができればよいですが,揉めることも少なくありません。
民法は,私人間の財産に関するルールや,相続に関するルールを定めています。相続のルールで基本となる事項は,誰がどのくらい遺産を受け取ることができるのかという取り分に関することです。それぞれの相続人が民法というルールに従って受け取ることのできる取り分のことを,「法定相続分」といいます。法定相続分を基準として,寄与分や特別受益を踏まえた相続分,遺留分の額が算出されます。
まずはざっくり法定相続分を確認していきましょう。
2 相続人になる者
被相続人の親族であれば誰もが相続人になるというわけではありません。相続人はその家族ごとの家族構成によって異なります。
まず,被相続人に配偶者がいれば,その配偶者が相続人となります。
次に,配偶者以外の親族,大まかに言えば,子,親(祖父母含む直系尊属。以下同様),兄弟については,相続を受け取る順位が決まっています。子が第1順位,親が第2順位,兄弟が第3順位となります。親は,第1順位たる子がいない場合(相続放棄などによって相続人ではなくなった場合も含む。)に,第2順位として相続人になります。兄弟についても,第1順位たる子と第2順位たる親がいない場合に,第3順位として相続人となります。
3 法定相続分
相続人が誰か分かれば,次に相続分がいくらなのかを決めることになります。
ざっくり説明すると,以下のとおりです。
① 配偶者と第1順位たる子 配偶者2分の1,子2分の1
② 配偶者と第2順位たる親 配偶者3分の2,親3分の1
③ 配偶者と第3順位たる兄弟 配偶者4分の3,兄弟4分の1
配偶者は当然1人ですが,子や親は2人以上のときもあります。例えば,子が2人いる場合,子の全ての取り分が2分の1となりますので,その2分の1の相続分をさらに2人の子で分ける(4分の1ずつ)ことになります。ちょっと難しくなりますが,同様の例で子の1人に代襲相続があり,孫が2人いる場合,子1人の4分の1の相続分をさらに2人の孫で分けることになるので,2人の孫はそれぞれ8分の1の相続分となります。
4 非嫡出子がいる場合
非嫡出子とは,法律上婚姻関係がない男女の間に生まれた子供のことをいいます。非嫡出子の相続分については,嫡出子の2分の1の相続分とする規定がありました。これが憲法に違反するという判決により法律改正があったことは有名だと思います。
その法律改正が施行された平成25年9月5日以降に開始された相続は,嫡出子と非嫡出子の区別なく同じ法定相続分となります。
では,この法律改正前の法定相続についてはどうなるでしょうか。
判決では,遅くとも平成13年7月当時に憲法違反があったので,これ以降は非嫡出子の規定の合理的根拠はないとしつつ,法的安定性の確保の観点から,法律関係が確定的になったものについては無効にならないとしています。つまり,平成13年7月より前の相続や平成13年7月から平成25年9月4日までの間の相続で確定したものについては,判決の影響が及ばないと考えられます。
5 まとめ
法定相続分は,相続人の取り分を決めるにあたっての基準になり得るものです。まずは,それぞれの相続に応じた相続人の取り分を定めた上で,協議によって遺産の処理を進めていければ良いでしょう。(あまり取り分を気にせずに気持ちよく分けるのが良いという場合もありますけどね。)