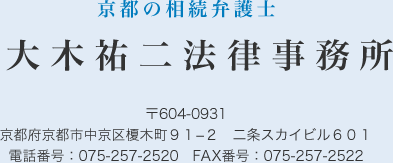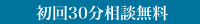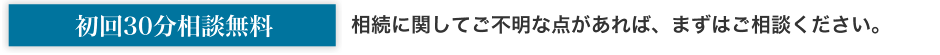相続コラム
特別受益請求の流れ
1 はじめに
特別受益制度は、具体的相続分の算定にあたって、相続人間の公平の観点からこれを調整するものです。皆さんが相続人だったとすると、皆さんの他の相続人が特別受益を受けた場合、どのようにこれを主張して具体的相続分に反映させるのでしょうか。今回は、特別受益の請求の方法についてお話します。
2 遺産分割協議
特別受益は実体法上の請求権ではないので、相続人に対して返還を請求することはできません。遺産分割の中でこれを主張することになります。
共同相続人は、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます(民法907条1項)。
3 遺産分割調停
遺産の分割において、共同相続人間に協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます(民法907条2項)。共同相続人は、調停の手続内で特別受益を主張することになります。
4 遺産分割審判
調停で当事者間に合意が成立する見込みがない場合や成立した合意が相当でないと認める場合には,調停が不成立となって調停が終了します(家事事件手続法272条1項)。調停が終了した場合,調停申立ての時に,遺産分割審判の申立てがあったものとみなされ(同条4項)、自動的に審判に移行します。
共同相続人は、審判において特別受益を主張することになります。
審判に不服がある場合は、即時抗告をすることができます(家事事件手続法286条1項及び2項、279条2項及び3項)。
この他にも,家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために公平の考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判をすることができます(家事事件手続法284条1項参照)。いわゆる「調停に代わる審判」というものです。審判をする場合,遺産分割の際に具体的相続分率の算出等があり審判書における理由の要旨を作成することが煩雑であり,時間がかかるなどのデメリットがあります。調停に代わる審判は,迅速かつ簡易に解決することができる制度です。調停に代わる審判には「相当と認めるとき」という要件があり,例えば,不出頭当事者がいる場合や,遺産の分割方法そのものについては当事者間に争いがない場合などが該当します。
5 特別受益と時効
特別受益は実体法上の請求権ではありませんので、時効によって特別受益を主張できなくなることはありません。遺産分割が完了しない限り、何十年前の贈与でも持戻しを主張することができます。
ただし,遺留分侵害請求権については,相続法改正により,共同相続人の1人になされた贈与が相続開始前の10年間になされたものであり,それが特別受益にあたる場合,特別受益の額を遺留分算定の基礎財産に算入します(改正民法1044条2,3項)
6 まとめ
一度遺産分割が完了すると、原則的にやり直すことはできず、ごく例外的な場合にのみやり直しが認められます。そのため、遺産分割の場面では、特別受益の有無について慎重な判断が求められます。相続が開始した早い段階で専門家に相談することをお勧めします。