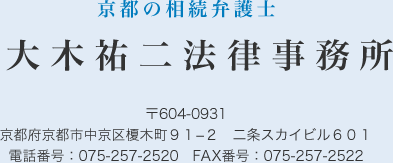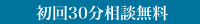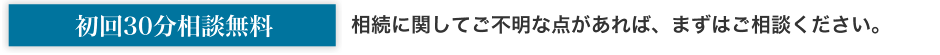相続コラム
遺言書がある場合の遺留分減殺請求
1 はじめに
原則として、財産の持ち主(被相続人)は、遺言により自己の財産を自由に処分することができます。しかし、その例外として「遺留分制度」というものがあります。今回は、遺言によって自由に処分できる財産の範囲についてお話します。
2 遺言とは
遺言とは、被相続人の最後の意思表示として、被相続人が単独で行う法律行為です。被相続人は遺言によって自由に自己の財産を処分することができます。遺言には民法によってさまざまな効力が認められている反面、遺言できる事項が明確に限定されています。遺留分に関連する事項は、具体的相続分の指定(民法902条1項)、分割方法の指定(民法908条)、遺贈(民法964条)の3つのものがあります。
3 具体的相続分の指定が遺留分を侵害する場合
⑴ 民法改正前
改正前の民法では、被相続人は、遺言によって共同相続人の相続分を定めることができました(民法902条1項)。ただし、遺留分に関する規定に違反することはできません(902条1項但書)。通説・判例の考え方から説明すると,「遺留分に関する規定に違反することができない」とは,遺留分侵害行為が単に侵害を受けた遺留分減殺請求に服せしめられると解し,遺留分減殺請求の結果,「遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が,その遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正される」(最決H24.1.26家月64巻7号100頁)こととなります(松川正毅・窪田充見編「新基本法コンメンタール-相続§民法882‐1044」62頁【木村敦子】)。よって、相続分を指定する遺言は遺留分侵害請求の対象になります。
そして、具体的相続分の指定が減殺されることで、共同相続人間の共有持分割合が変更されるという効力が生じます。
ここで言う共有とは遺産共有ではなく物権の一般的な共有状態を指します。分割の際には、原則として、遺産分割手続(民法907条)ではなく、共有物分割訴訟の手続(民法258条)を行うことになるので注意が必要です。
⑵ 民法改正後
民法改正後には、「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」に変わります。遺留分侵害額請求権を行使することによって,遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じます。つまり,遺留分権利者が自己の固有の財産として保持することになり,改正前のような共有状態にはなりません。遺留分侵害額請求権を行使するためには訴えの方法を用いる必要はありませんが、相手方がこれに応じない場合には訴訟を提起することが考えられます。その場合の訴訟は,金銭の給付を請求するもの(給付訴訟)となります。
このような改正により,民法902条1項但書「遺留分に関する規定に違反することができない」という箇所が削除されました。これは、改正前は相続人の指定相続分が遺留分を侵害する部分について、相続分が修正されてしまうため「遺留分に関する規定に違反することができない」と規定されていたのが,改正後には、遺留分を侵害しても金銭債権が生じるにすぎないため「遺留分に関する規定に違反する」という事態が生じないからです。
4 分割方法の指定が遺留分を侵害する場合
被相続人は、遺言によって遺産を分割する方法を定めることができます(民法908条)。分割方法の指定は,本来的には,法定相続分をそのままにして遺産をどのように割り振るかについての方法を定めたものです。そうすると,単なる分割方法の指定をしただけであれば,遺留分を侵害することはないように思うかもしれません。
ですが,実際には,分割方法だけでなく,特定の財産の承継先となる相続人を指定したものが多く(特定財産承継遺言),このような場合であれば上記3と同様に考えることができます。
ちなみに、民法改正によって、「特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人」も遺留分侵害請求権の対象になることが明文化されます(改正民法1046条1項括弧書)。
5 相続させる旨の遺言
遺言実務では、「特定の財産を、特定の相続人に、相続させる」旨の遺言がされることが多くあります。この遺言は、原則として、4の分割方法の指定としての性格を持ち、相続開始によって直ちに分割の効力が生じると解されます。そしてこれが他の共同相続人の遺留分を侵害するときは、遺留分減殺請求の対象になります(最判平成3年4月19日民集45巻4号477頁)。
この遺言が減殺されることで、特定の財産について、受遺者の単独所有を離れて、共同相続人の共有状態が発生するという効力が生じます。
以上は民法改正前のものとなりますが、民法改正により、特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言に関しては「特定財産承継遺言」(改正民法1014条2項)として明文化され、特定遺贈の場合とほぼ同様に扱うことになります。また,遺留分侵害請求についても,上記3と同じような考えとなります。
6 遺贈が遺留分を侵害する場合
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができます(民法964条)。ただし、遺留分に関する規定に違反することはできません(同条但書)。
① 特定遺贈が遺留分を侵害するとして減殺された場合は、当該財産について共同相続人間で、物件法上の共有状態が発生します。
② 相続人の相続割合を変更する形で包括遺贈がなされて、これが減殺された場合は、この持分割合が変更されるという効力が生じます。
③ 特定の相続人に対する全部包括遺贈がされて、これが減殺された場合は、特定遺贈と同様に、個々の財産についての物件法上の共有状態が生じます(最判平成8年1月26日民集50巻1号132頁)。
7 民法改正における変更点
具体的な相続分の指定であったり,遺産分割方法の指定であったり,相続させる旨の遺言であったりと様々な側面から遺留分や遺言について説明しましたが,遺言によってはいろんな側面を有するものもあるので,きれいに区分けできないこともあります。
2018年の民法改正によって遺留分減殺請求権は、遺留分侵害額請求権へと変更されます。この権利の行使によって、遺留分侵害額に相当する金銭の給付を目的とする債権が発生します。従来の共有状態が生じるという効果とは異なりますので、注意が必要です。個人的には,遺留分侵害額請求権という金銭給付の性格を持つようになったことから、以前より改正後の制度のほうが分かりやすくなったのかなとは思います。