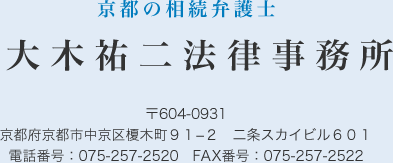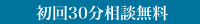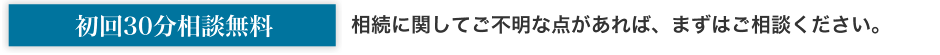相続コラム
相続税の延滞税・加算税
1 相続税の附帯税
親族が亡くなり、財産を相続した場合、相続税を納めなければなりません。
相続税については、相続の開始があったこと、つまり、被相続人(亡くなった方)が亡くなったこと、を知った日から10か月以内に確定申告と納付をしなければなりません。
この期限内に申告や納付をしなかった場合や、申告や納付をした相続税額が本来納めるべき税額より少なかった場合は、ペナルティとして追加で課税されることがあります。
今回は、この追加で課される税金(附帯税といいます)についてお話しします。
2 附帯税の種類
附帯税には、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税、延滞税があります。
⑴ 無申告加算税
申告期限内に申告しなかった場合に発生するものです。期限が過ぎても税務調査通知前に自主申告した場合には、本来納付すべき税額に対して5%の額の加算税が課されますが、税務調査の通知を受けた後、さらに税務調査を受けた後に申告した場合にはさらに高い割合で課されることになります。
ただし、申告しなかったことについて正当な理由があると認められる場合には、無申告加算税は課されません。
⑵ 過少申告加算税
申告した相続税の額が本来納付すべき税額より少なかった場合に発生するものです。
期限が過ぎても税務調査通知前に自主申告すれば、過少申告加算税は課されません。税務調査の通知後や、税務調査後に申告した場合は、そのいずれであるかに応じて割合が決定されます。
⑶ 重加算税
相続財産を意図的に隠したり虚偽の申告を行なったりした場合に発生するものです。意図的に税額を少なくしようとするものですから悪質性が高いとして、その税率も高くなっています。
具体的には、本来納付すべき税額に対して、無申告の場合は40%、過少申告の場合は35%です。
⑷ 延滞税
申告は期限内にしたものの、納付が期限に遅れた場合や一部しか納付しなかった場合に発生するものです。本来の税額に不足する金額に対して日割計算されます。
税率は二段階で設定されており、時期によっても異なります。
3 遺産分割協議がまとまらない場合
申告・納付期限内に遺産分割が終了せず、自分の相続する財産が確定しない(従って納めるべき相続税の額が定まらない)こともありますが、それは申告・納付をしない「正当な理由」としては認められません。このような場合には、ひとまず法定相続分で申告・納税した上で、遺産分割が確定した後に改めて税額の減少・増加を申告して訂正する必要があります。
4 おわりに
以上みてきたように、相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内に、申告・納付しなければなりません。これを正しく行わない場合はペナルティとして追加徴税されてしまいますので、注意が必要です。