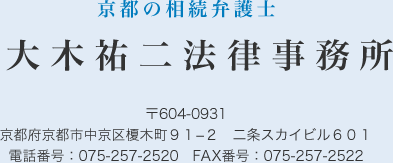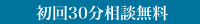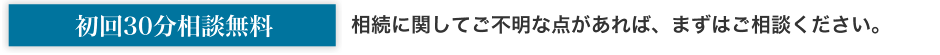相続コラム
特別受益の持戻し
1 はじめに
相続人が受け取った財産が特別受益に当たる場合は、まずは相続開始の時点で有していた財産の価額に、この特別受益のうちの贈与の価額を加えます。その加えた財産を相続財産とみなします。みなし相続財産を法定相続分に従って共同相続人に割り振った後に、特別受益(贈与・遺贈)の額を控除します(民法903条1項参照)。
このような制度を「特別受益の持戻し」と言います。言葉の印象から、特別受益たる贈与や遺贈が相続財産に戻されるという意味だと思われるかも知れませんが、法律上は特別受益のうち贈与の額が加わるに過ぎません。また、贈与された財産が相続財産に返還されるようにも見えますが、単に贈与された額が相続財産に加算されるだけです。「特別受益」の「持戻し」という単語の意味にとらわれず、「特別受益の持戻し」という制度として上記のようなものであると理解した方が良いでしょう。
今回は、この特別受益の持戻しの算定方法について具体例を挙げてお話しします。
2 特別受益があった場合の具体的相続分の計算方法
特別受益の算定は以下の方法によって行います。
| 被相続人Xが、⑴4000万円の土地、⑵1000万円の債権、⑶500万円の債務を負っていました。相続人は、A、B、Cの三人の子です。Xは、生前、Aが開業する資金として1000万円をAに与えていました。Xは、Bに対し、1000万円を遺贈しました。 |
① 特別受益の額を確定する
特別受益の対象は、「遺贈」、「婚姻若しくは養子縁組のため」の贈与、「生計の資本として」の贈与がこれに当たります。相続人は、これらの現在の価値を基準として、これらを持ち戻さなければなりません。これについては回を改めてご説明することにします。
② みなし相続財産の額を確定する
ア 債務の扱い
みなし相続財産を算定する基礎になる「相続開始時において有した財産の価額」(903条1項)は債務を含みません。よって、ここでは、5000万円(土地4000万円+債権1000万円)を基礎に、みなし相続財産を算定します。
イ 遺贈の扱い
遺贈とは、被相続人が相続開始時に有していた財産を、特定の者に譲渡する行為なので、「相続開始時において有した財産の価額」(903条1項)に、すでに含まれています。よって、遺贈された財産は、特別受益にあたりますが、加算(「持戻し」とも説明しているものもある。)の対象にはなりません。
これに従って、みなし相続財産を算定すると
(みなし相続財産)=「相続開始時時において有した財産の価額」+「特別受益(贈与)」
=5000万円+(Aに対する贈与)
=5000万円+1000万円
=6000万円
よって、ここでは、みなし相続財産は6000万円となります。
③ ②の額を前提に具体的相続分を計算する
ABCの法定相続分は各3分の1なので(民法903条1項、900条)、ABCは、各2000万円を取得します。ここから、特別受益の価額を控除します。すると、ABCの各具体的相続分は以下のようになります。
(Aの具体的相続分)=2000万円-(特別受益(贈与・遺贈)の額)
=2000万円-(Aに対して贈与された額)
=2000万円-1000万円
=1000万円
(Bの具体的相続分)=2000万円-(特別受益(贈与・遺贈)の額)
=2000万円-(Bに対して遺贈された額)
=2000万円-1000万円
=1000万円
(Cの具体的相続分)=2000万円-(特別受益の額)
=2000万円-0円
=2000万円
よって、ABCは、相続開始の時において有した財産から遺贈された額を控除した額である4000万円を1:1:2の割合で取得します。つまり、Aが、1000万円、Bが1000万円、Cが2000万円を取得し、Bは、これとは別に遺贈として1000万円を受け取ることになります。
3 持戻しの免除
特別受益制度では、被相続人の意思によって、持戻しを免除することができます(903条3項)。例えば、被相続人が相続人に対して生前贈与の場合、相続分とは別に贈与したということであれば、被相続人には持戻し免除の意思があったと言えます。また、遺贈についても持戻しの免除と言われますが、先ほど説明しました通り、特別受益にあたる遺贈は相続財産額に加算せず、みなし相続財産から一応の相続分を確定し、その一応の相続分から遺贈額を控除するという扱いがなされるため、遺贈に関する持戻しの免除は、一応の相続分から遺贈額を控除しないという被相続人の意思表示を指します。ここでも、「持戻し」の本来の意味に固執してしまうとややこしいことになるので、このような制度であると割り切ったほうが良いかと思います。
ただ、持戻しの免除の意思表示があったとしても、遺留分を害することはできません(遺留分については別の回でご説明します)。
上の例で、仮に、XがAの持戻しを免除する意思表示をすると、Aは、1000万円を持ち戻す必要がなくなります。みなし相続財産は5000万円となり、Aは、これの3分の1を取得することができます。
4 改正による変更点
平成30年の相続法改正によって、903条4項が新設されます。婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときは、持戻しの意思表示があったものと推定されます(改正民法903条4項参照)。
5 特別受益が法定相続分を超える場合
特別受益が法定相続分を超える場合は、計算が少し難しくなります。これも具体例を挙げてみましょう。
| 被相続人Xが、5000万円の現金を有していました。相続人は、妻A、子B、子Cの三人の子です。Xは、Aに対し、1000万円を遺贈しました。Xは、生前、Bに対し、Bが開業する資金として3000万円を与えていました。 |
これを前提にABCの具体的相続分を計算してみましょう。
(みなし相続財産)=「相続開始時時において有した財産の価額」+「特別受益(贈与)」
=5000万円+(Bに対する贈与)
=5000万円+3000万円
=8000万円
(Aの具体的相続分)=(法定相続分:2分の1)-(特別受益(遺贈・贈与)の額)
=4000万円-(Aに対して遺贈された額)
=4000万円-1000万円
=3000万円
(Bの具体的相続分)=(法定相続分:4分の1)-(特別受益(遺贈・贈与)の額)
=2000万円-(Bに対して贈与された額)
=2000万円-3000万円
=-1000万円(???)
(Cの具体的相続分)=(法定相続分:4分の1)-(特別受益(遺贈・贈与)の額)
=2000万円-0円
=2000万円
このとき、Bの具体的相続分はマイナスになります。特別受益を控除した結果がマイナスになった場合は、受遺者又は受贈者は、その相続分を受け取ることができません(民法903条2項)。しかし、マイナスになった相続人は、差額を返還する義務を負うものではありません。
よって、ABCは、3:0:2の割合で相続開始の時において有した財産5000万円から遺贈された額1000万円を控除した額を分け合うことになります。
(Aの具体的相続分)=(相続開始時の財産)×3/5
=4000万円×3/5
=2400万円(なお、Aはこの他に遺贈として1000万円を受け取っている。)
(Bの具体的相続分)=(相続開始時の財産)×0/5
=4000万円×0/5
=0円
(Cの具体的相続分)=(相続開始時の財産)×2/5
=4000万円×2/5
=1600万円
以上のようになります。
6 まとめ
今回は簡単な事例でご説明しましたが、実際に特別受益の額を算定するときは、事案ごとに様々な事情を考慮します。そのため、遺産分割の場で特別受益を主張する際は、早い段階で専門家に相談することをお勧めします。