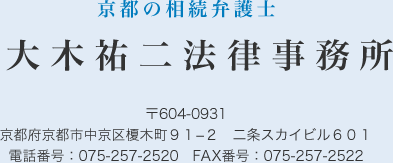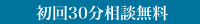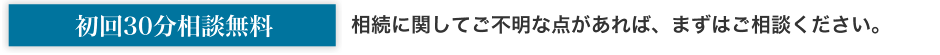相続コラム
特別受益の対象となる財産
1 はじめに
相続人が受け取った財産が特別受益に当たるか否かは、持戻しをしなければならないかどうか、遺留分減殺請求権の期間制限があるかどうかに関わるので、相続人にとっては非常に重要な問題です。民法第903条1項では,「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき」には,これらを特別受益として相続人間の不公正を是正するような処置が規定されています。今回は、被相続人から財産を譲り受けた場合、具体的にどのような財産が特別受益に当たるのかについてお話します。
2 「遺贈」
遺贈は当然に、特別受益に当たります。
3 「婚姻若しくは養子縁組のため」の生前贈与
婚姻や養子縁組のための贈与ならば、常に特別受益となるわけではありません。そもそも特別受益制度の趣旨は、遺産の前渡しによる相続人間の不公正を是正することです。遺言の前渡しとは言えない場合には、特別受益とはなりません。一般的に、結納金や挙式費用、持参金などはこれにあたらないと言われます。
4 「生計の資本」としての生前贈与
贈与の目的、金額、他の相続人との関係で、実質的に扶養義務の範囲を超えるかどうかによって判断します。
① 生活費の援助
親から子への生活費の援助は、親の扶養の範囲といえるので、特別受益とは言えないでしょう。
② 学費
高校や大学の学費は、一律ではなくその家庭の経済的事情によって判断されることになります。一般には、私立大学程度ならば特別受益にあたらず、私立の医学部や留学費用などは特別受益になり得ると言われます。被相続人の資産状況や社会的地位に照らして扶養義務の範囲内か否かを見ることになります。
③ 各種資金
住宅資金や独立開業費用も特別受益となる可能性があります。
④ 金銭以外のもの
金銭だけでなく、土地や建物の贈与やこれらの無償使用も扶養義務の範囲を超えるものとして特別受益にあたる可能性があります。
5 まとめ
受け取った財産が特別受益にあたるかどうかの判断は、その事案の被相続人の資産状況や社会的地位,金額,贈与された内容など具体的な事情に即して判断されます。基準があいまいであるため争いが生じやすい分野でもあるでしょう。上記以外にも生命保険金請求権や死亡退職金が特別受益に該当するかという難しい判断がなされることもあります。早期の段階で専門家に相談することが重要でしょう。