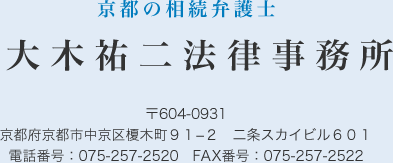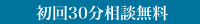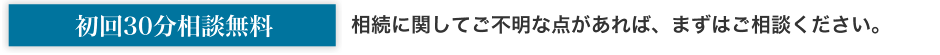相続コラム
遺留分減殺請求を受けた場合
1 はじめに
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者に認められた権利です。よってこれを請求された場合には応じなければなりません。しかし遺留分の侵害額の算定や相続財産の評価が困難であるため、請求された段階では根拠が不明確な場合も多くあります。また、適切に対応すれば請求を拒んだり請求を減額させたりできる場合もあります。今回は、遺留分減殺請求を受けた場合の対処の仕方についてお話しします。
2 現物返還の原則
遺留分減殺請求権は、対象となる贈与や遺贈の効力を(部分的に)否定する権利なので、その効果は、現物の返還が原則です。現金の場合は、請求を受けた者(以下「相手方」といいます。)は、現金を支払わなければなりません。
贈与、特定遺贈や全部包括遺贈に対して遺留分減殺請求権を行使された場合は、対象の財産について物権法上の共有状態が生じるので、共有物分割請求(民法258条2項)によって共有関係を清算することになります。
相続分の指定や割合的包括遺贈に対して遺留分減殺請求権を行使された場合は、通常の遺産分割手続きによることになります。
≪共有物の分割について≫
民法258条は現物分割と競売による換価分割を規定します。しかし、判例によって部分的価格賠償や全面的価格賠償が認められています。つまり、物権法上も、金銭によって割合的に調整することが可能です。
3 価額弁償(その1)
現物返還が不可能な場合は、価額弁償をしなければなりません。減殺を受けるべき受贈者は、第三者に目的物が譲渡された、又は目的物に第三者の権利(抵当権や地上権など)が設定された場合は、価額を弁償しなければなりません(民法1040条各項)。これは受遺者にも類推適用されます。
4 3で支払わなければならない価額の算定方法
3の場合、相手方は、「遺留分権利者が減殺請求権の行使により当該遺贈の目的物につき取得すべきであった権利の処分額が客観的に相当と認められるものであった場合には、その額を基準」(最判平成10年3月10日民集52巻2号319頁)として価額を支払うことになります。
5 価額賠償(その2)
3の場合でなくても、相手方から価額弁償を選択することもできます。(「受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して、現物返還の義務を免れることができる」)(民法1041条)。目的物である財産が既に生活の基盤になっている場合や、事業承継のために事業用資産を相続人の一人に承継させた場合は、これによって現物返還を免れることができます。
6 5で支払わなければならない価額の算定方法
5の場合、相手方は、「現実に弁償がなされる時の目的物の価額であり、また、遺留分権利者において当該価額弁償を請求する訴訟にあっては現実に弁償される時に最も接着した時点としての事実審口頭弁論終結時」(最判昭和51年8月30日民集30巻7号768頁)の目的物の価額を支払うことになります。
このとき、相手方は、単なる価額弁償の意思表示では足りません。価額弁償の現実の履行、又は弁済の提供までしなければならないことに注意が必要です。
7 時効に関する注意点
遺留分減殺請求権は、原則として、請求権者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年の経過で時効によって消滅します(民法1042条)。贈与が特別受益に当たる場合には例外として時効によって消滅しません。しかし、その判断が難しい場合が多いです。
時効が完成していれば、相手方はこれを援用することができます。時効の完成を知っているいないにかかわらず、一度相手方の請求権を認めてしまうと、後で時効が完成していたとわかっても、消滅時効を援用することができなくなる可能性があるので注意が必要です。既に時効が完成していると思われる場合は、交渉などを行わない方がよいでしょう。
8 民法改正による変更点
2018年の民法改正によって、遺留分減殺請求権は2019年7月1日から遺留分減殺額請求権へと変更されます。この権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭の給付を目的とする債権が発生します。従来の、共有状態が生じるという効果とは異なりますので、注意が必要です。