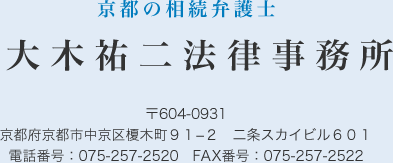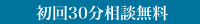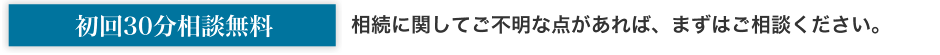相続コラム
相続税の各種控除
1.相続税の各種控除
相続税の計算をする場合には、相続人ごとに税金額を減らすことができる様々な制度(控除)があります。相続人が亡くなった方の配偶者である場合の“配偶者控除”、相続人が未成年である場合の“未成年者控除”などが代表的なものです。相続人ごとの相続税額を計算したあと、これらの控除を相続人ごとに適用した結果が、実際に納める相続税額となります。
2.配偶者控除
相続人が亡くなった方の配偶者である場合、次の2つの金額のうち、金額が多い方の相続税を減少させる制度が「配偶者控除」です。
① 1億6,000万円
② 配偶者の法定相続分
例えば財産額が1億円で、相続人が配偶者と子どもである場合は「1億6,000万円>1億円×1/2=5,000万円」となり、1億6,000万円まで相続税がかからないこととなります。そのためこのケースでは、すべての財産を配偶者が取得した場合には、相続税を納める必要がなくなります。
なお、この制度を受けるためには、「遺産分割が完了しており、かつ、相続税の申告書を提出すること」が必要となります。遺産分割が完了していない場合は、一定の手続を行うことで、後日、遺産分割が完了したタイミングで制度の適用を受けることができます。
3.未成年者控除
相続人が未成年者(20歳未満)である場合、未成年者控除として次の金額の相続税を減少させる制度が「未成年者控除」です。
(20-相続発生時の年齢)×10万円
相続発生時の年齢は1年未満の端数は切り捨てますので、例えば18歳10か月の場合は18歳として計算し、(20-18)×10万円=20万円の相続税を減少させることができます。
なお、この制度は法定相続人である未成年者にしか適用がありませんので、例えば遺言で法定相続人ではない孫等が財産を取得した場合には、適用がありません。
また、現在は20歳未満を未成年者と定義されていますが、今後未成年者の定義が18歳未満に変更されたような場合には、それに伴って18歳未満の場合に適用されるようになります。
4.障害者控除
相続人が障害者である場合は、障害者控除として次の金額の相続税を減少させる制度が「障害者控除」です。
(85-相続発生時の年齢)×10万円
相続発生時の年齢は1年未満の端数は切り捨てますので、例えば45歳7か月の場合は45歳として計算し、(85-45)×10万円=400万円の相続税を減少させることができます。
また、特別障害者の場合、1年あたり20万円として控除額を計算します。
なお、この制度は法定相続人である障害者にしか適用がありませんので、例えば遺言で法定相続人ではない障害者が財産を取得した場合には、適用がありません。
5.控除しきれない控除額の取扱い
未成年者控除や障害者控除の金額が、その相続人のもともとの相続税額よりも大きく、控除しきれないというケースもあります。この場合、その控除しきれない金額を、その未成年者や障害者の一定の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
例えば、相続人が子どもAと子どもBの2人、相続税額は2人とも200万円、子どもAが障害者で60歳、子どもBが一定の扶養義務者であった場合の計算は次のようになります。
① 子どもAの障害者控除 (85-60)×10万円=250万円
② 子どもAの相続税額 200万円-200万円=0円
③ 控除しきれない障害者控除額 250万円-200万円=50万円
④ 子どもBの相続税額 200万円-50万円=150万円