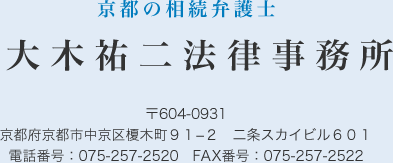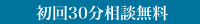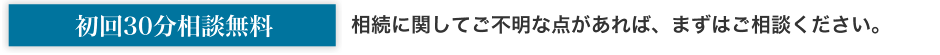相続コラム
遺産分割協議の有効性
1 はじめに
人が死亡すると、相続が開始します。被相続人(亡くなった人)の財産(債務等の消極財産を含む)は相続開始と同時に相続人に移転します。
被相続人とどのような関係にある人が相続人となるかどうかは、法律によって定められていますが、相続人が複数であることは少なくありません。相続人が複数の場合には、相続開始時には相続の対象となる財産が一旦相続人全員(共同相続人)の共有に属します。共同相続人の共有にある財産は、相続人のひとりが単独で処分するようなことはできません。
そこで、この共有状態にある相続財産を各相続人に分割・分配して、相続人それぞれに一定の財産を帰属させる必要があります。この分配の手続を、遺産分割といいます。
遺産分割は、共同相続人の協議、つまり話し合いによって行われることが原則です。これではうまくいかない場合に、裁判所の関与を得て、調停や審判で分割することもあります。
遺産分割は、亡くなった方の財産をだれがどれだけどのように相続するか、を決める手続ですから、相続人間や親族間での利害や感情が対立し、紛争が深刻化・長期化することがままあります。そして、その手続は、各相続人が対等に関与し、その意思を反映させる形で、公正に行われるべきです。したがって、相続人の一部しか参加せずに遺産分割の協議をしてしまったり、誰かが誰かをだましていたりする場合には、その協議の効力を否定して、公正な形で手続きをやり直す必要があります。
今回は、遺産分割協議の手続に問題があるために、遺産分割協議の効力が否定される場合について、お話しします。
2 相続人全員が参加しない場合
遺産分割協議は、共同相続人全員の自由な意思の合致によって、なされる必要があります。したがって、共同相続人全員が参加し、自由な意思によって協議・合意したといえない場合には、協議は無効になります。
まず、法律で定められる相続人全員が参加している必要があります。誰かを排除して協議を行い合意をしても、それは効力を持ちません。
これは、相続人の一人が所在不明であっても同じです。行方が知れないからといってその人を抜きにして協議をすることはできません。そのような場合、不在者財産管理人の選任という制度などを用いることで、有効な遺産分割協議をすることができます。
さらに気を付けなければならないのは、未成年者とその親権者が両方とも共同相続人である場合です。通常未成年者が相続人である場合は、その親権者が代理人として手続に参加します。しかし、自分自身も相続人であるのに、別の相続人の代理人として協議に参加することは、認められません。このような行為を「無権代理」といいます。未成年者とその親権者が両方とも共同相続人である場合には、未成年者の特別代理人を選任する必要があるのです。
また、遺産分割協議後に、協議に参加していなかった者が実は相続人であることが判明したり確定したりすることがあります。婚姻や養子縁組の無効、親子関係不存在確認、認知などの裁判が確定した場合、相続人に当たる者の範囲が変わってくる可能性があります。このような場合には、遺産分割協議当時には相続人とされていなかったとしても、遡って相続人であったこととなり、その相続人が協議に参加していなかったとして、協議が無効になります。(ただし、認知などの場合には、すでにされた遺産分割を無効とせずに、新たに相続人であることが確定した者がその相続分に応じた支払請求権を取得する、という仕組みになっています。)
さらに、遺産分割協議には、相続人以外の者が参加することは認められません。相続人ではない者が参加していた場合(特に、相続人だとされていた者が、その後の裁判で相続人ではないことが確定したような場合)には、遺産分割協議が無効とされる可能性があります。ただし、無資格者に分割された部分のみが無効となり、その部分について再分割が行われるという可能性もあります。
3 意思表示の無効・取消事由がある場合
遺産分割協議に参加していた相続人の意思表示に瑕疵(間違いや問題)があった場合には、その意思表示が無効とされるか、取り消されることによって、遺産分割協議自体も無効となる可能性があります。
具体的には、まず、相続人が意思無能力者(民法3条の2)であった場合、制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)であった場合です。これらの場合には、意思表示の前提となる判断能力が欠けており、その意思表示が無効とされるか取り消される可能性があります。
また、相続人が真意とは異なる意思の表示をした場合も問題になります。真意とは異なる表示をした相続人のみがそのことを知っていた場合(心裡留保;民法93条)は無効にはなりませんが、他の相続人がこれを知っていた場合や、通謀した場合(虚偽表示:民法94条)は、無効とされます。
さらに、相続人が、自分の表示している内容を誤って認識していた場合や、意思形成の基礎とした事情に誤認があった場合(錯誤:民法95条)も、一定の条件のもと取消が認められます。また、詐欺や強迫(民法96条)によって意思表示をしていたという場合も、取消の対象となります。意思表示が取り消されるとその意思表示は無効であったこととなります。
これらの場合には、遺産分割協議の基礎となった意思表示が無効となる結果、遺産分割協議そのものが無効となる可能性があるのです。
4 おわりに
以上のように、遺産分割協議の手続に問題がある場合、これが無効となる結果、協議をやり直さなくてはなりません。
遺産分割協議を行なうにあたっては、まず相続人が誰であるのかを確定し、各相続人に問題はないか、遺産分割協議をするに当たって何かしらの問題はないかなどを慎重に確認して、手続きを進めていく必要があります。