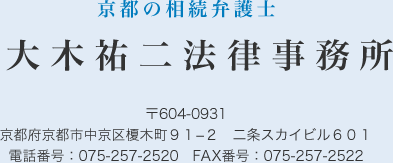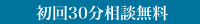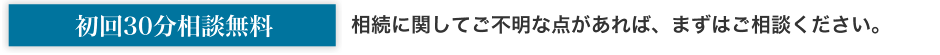相続コラム
相続税の計算方法
1 はじめに
相続税法は、相続税の計算方法について規定しています。その内容について説明します。
2 遺産総額の算出
加算する事項―本来の相続財産
本来の相続財産とは、相続の開始によって被相続人から相続人に移転する積極及び消極の財産の総額をいいます。すべての財産を金銭価値に換算して集計する必要があり、例えば土地や建物などの不動産もそれぞれ何円の価値があるのかという換算をして集計を行います。
加算する事項―みなし相続財産
みなし相続財産とは、被相続人の死亡を契機として生じる財産をいいます。具体的には、保険金や退職手当金等がこれに当たります。
加算する事項―生前贈与
相続が発生する前3年以内に贈与が行われていた場合は、その贈与財産の額を加算します。
加算する事項―相続時精算課税適用財産
相続時精算課税制度を利用する場合に限り加算します。選択を開始した時期から相続が開始された時期までの贈与財産を全て加算することになります。
減算する事項―非課税となる財産
非課税の対象となる財産は、相続税法12条に7種類規定されています。例えば、墓所、霊廟及び祭具などが該当します。また、相続により取得した生命保険金の合計額のうち、500万円に法定相続人数を乗じた額を限度として、非課税となります。
減算する事項―債務
貸金債務などが挙げられます。
まとめ
(各相続人の課税価格)=(本来の相続財産)+(みなし相続財産)+(3年以外の贈与)+(相続時精算課税適用財産)ー(非課税財産)―(債務)
3 基礎控除額の控除
減算する事項―基礎控除額
基礎控除額は、相続税法15条2項のとおり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という式で計算されます。例えば法定相続人が3人の場合は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
この基礎控除の計算上の注意点としては、法定相続人の数を数える際の「養子」の数え方です。特別養子縁組の場合は、他の法定相続人と同様に単純に人数をカウントしますが、普通養子縁組の場合は異なります。普通養子縁組では、相続人に実子が含まれる場合は最大で1人までしかカウントせず、相続人に実子が含まれない場合でも最大で2人までしかカウントされません。そのため、例えば相続人が配偶者・実子1人・普通養子縁組の養子3人という場合は、配偶者1人・実子1人・養子1人の計3人としてカウントし、基礎控除額は4,800万円となります。
まとめ
控除した額が、課税対象の遺産総額ということになります。
4 相続税の算出
法定相続分に基づく、各相続人の相続税額の算出
以下の表に基づき算出します。その後、それを合算します。
| 各相続人の取得金額 | 税率 |
| 1000万円以下 | 10% |
| 1000万円超~3000万円以下 | 15% |
| 3000万円超~5000万円以下 | 20% |
| 5000万円超~1億円以下 | 30% |
| 1億円超~2億円以下 | 40% |
| 2億円超~3億円以下 | 45% |
| 3億円超~6億円以下 | 50% |
| 6億円超 | 55% |
相続税の計算においては、実際にどのような遺産分割が行われたかにかかわらず、一度、法定相続分によって相続がされたと仮定して、相続人ごとの遺産の取得額の算定を行います。相続税の税率は累進税率となっており、金額が大きくなるほど税率が高くなります。そのため、このように一度、法定相続分で相続したと仮定して相続人ごとに計算することは、納税者にとって有利になる計算方法となります。
例えば、配偶者と子のみが相続人であった場合、各々1/2の法定相続分を有するため、3で算出した課税対象の遺産総額の半分の額について、相続税を算出します。
各相続人の相続税額の合算
上記⑴の例では、配偶者と子の各相続税額を足し合わせます。
各相続人の納付すべき相続税額の算出
実際に行われた遺産分割に基づいて相続人ごとの相続税の対象財産の取得額を算定します。そして、相続税の対象財産の合計額に対するその取得額の割合を計算し、その割合を上述の相続税の総額に掛けて、相続人ごとの相続税額を計算します。その金額から、各種の控除を適用したあとの金額が、相続人ごとに納付すべき相続税額となります。
上記⑴の例で、実際の配偶者の相続分が3/4、子の相続分が1/4であった場合、⑵で算出した相続税額につき、実際の相続分に従って相続税を按分します。