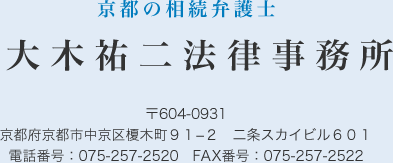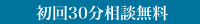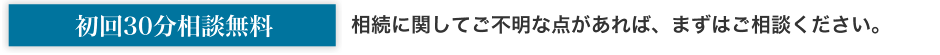相続コラム
生前贈与と遺留分減殺請求権
1 はじめに
被相続人は、生前に、自分の財産を自由に贈与することができます。遺留分権利者は、この贈与に対して減殺請求をします。遺留分減殺請求の対象は、遺贈及び贈与です(民法第1031条)。今回は、どのような贈与が減殺の対象になるのか、いつの時点の贈与が対象になるのか等についてお話します。
2 遺贈と贈与
遺贈と贈与は似ていますが、法的には全く異なります。遺贈とは、被相続人(正確には遺贈者)が遺言によって財産を第三者に譲渡する行為なので,被相続人単独で行うことができます。一方、贈与とは、被相続人(正確には贈与者)が契約によって財産を第三者に譲渡する行為なので,財産を贈与する人と受け取る人との合意によって成立するものとなります。
似たようなもので死因贈与というものもあります。これは贈与ということで契約に該当しますが,贈与者の死亡によって効力が生じるもの(停止条件付贈与)であるため,効力の発生時期については遺言で行われる遺贈と似たようなものになります。
3 何が生前贈与なのか
贈与とは、「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受領すること」(民法第549条)、つまり、無償で財産を与えるということです。有償であっても財産の対価が不当な場合は、これが贈与とみなされる可能性があります(民法第1039条)。
4 相続人に対する生前贈与
被相続人が生前、他の相続人に財産を贈与していた場合、自己の遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求権を行使することができます。しかし、全ての贈与に対して権利を行使できるわけではなく、被相続人が死亡してから一年前にされた贈与に限られます(民法第1030条)。
ここで、期間制限のかからない場合が二つあります。
一つは、贈与の当事者双方が、遺留分を侵害することを知っていた場合です(同項但書)。ここでは簡単な説明に留めますが,「遺贈・贈与の事実を知っていた場合」とは別であることにご注意ください。
もう一つは、その贈与が特別受益にあたる場合です(特別受益については後述します
)。贈与が特別受益にあたる場合は、民法1030条が適用されないため、原則として、減殺請求の対象となります(民法1044条、903条)。ただし、例外的に、「相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会的経済事情や相続などの関係人の個人的事情をも考慮するとき、減殺請求を認めることが相続人に酷であるなどの特段の事情」があるときは減殺請求の対象になりません(最判平成10年3月24日民集52巻2号433頁)。
ちなみに、相続人以外の第三者に対する贈与の場合も、民法1030条の通り、1年の期間制限があります。
5 特別受益
生前贈与が特別受益にあたる場合は、特段の事情がない限り、一年以上前の生前贈与も減殺の対象にすることができます。
特別受益とは、被相続人から共同相続人に対して遺贈された財産や、婚姻や養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与された財産を言います。金額によって結論が異なってきますが,持参金や結納金、居住用不動産や独立した子の生計への資金援助などがこれに該当する可能性があります。また,高等教育の学費も、被相続人の資力や社会的地位に照らして扶養義務の範囲を超えると認められる場合には、特別受益に当たる場合があります。
特別受益の場合は、被相続人が持戻しを免除する意思表示をすることで、贈与した財産を特別受益から外すことができますが、遺留分に民法1044条によって準用される場合は、持戻し免除の意思表示があっても減殺の対象になります。
なお、民法改正により、相続開始時の10年前までになされた特別受益が遺留分額算定の対象になります。詳細は別途お話しいたします。
6 減殺の順序
遺留分が侵害されたとき、まずは遺贈から減殺します。遺贈を減殺してもなお侵害額がある場合に贈与を減殺することができます(民法1033条)。複数の贈与が請求の対象になる場合は、最も遅い贈与から順次前の贈与に対して減殺します(民法1035条)。
ちなみに、死因贈与は、遺贈の次、贈与の前に減殺します(東京高判平成12年3月8日高民集53巻1号93頁)。
7 まとめ
このように、生前贈与が特別受益に当たるか否かによって、減殺請求できる期間が変わります。この特別受益に当たるかどうかは個別具体的な事情によって判断されるので、専門家に相談することお勧めします。