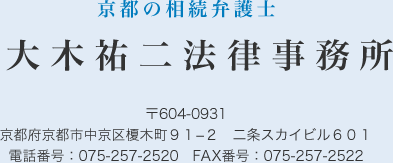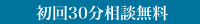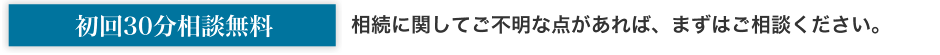相続コラム
相続税とは
1.はじめに
日本には様々な種類の税金があり、納付先も国や都道府県や市町村など、税金によって違ってきます。そうした税金のうち国に納めるもののひとつが相続税です。
相続税とは、亡くなった方(被相続人)の遺産(相続財産)を相続によって取得した場合や、遺言によって取得 (遺贈) した場合に、その取得した相続財産の額を基礎としてかかる税金のことをいいます。
しかしながら、すべての相続について必ずしも相続税がかかるというわけではなく、その相続財産の額が「基礎控除」を上回る場合に、相続税がかかります。
なお、相続税の申告率ですが、おおよそ8%となっており、概ね12.5件に1件の比率となっています。
2.納税義務者
税金を納める義務がある人のことを納税義務者といいます。
相続税は、上述のように、相続等によって相続財産を取得した場合にかかる税金ですので、その相続財産を取得した人が納めることとなります。
逆に言えば、相続人であったとしても、財産を1円も相続等により取得していない人は、相続税を納める必要がありません。
3.申告期限、納期限
税金には申告書の提出期限(申告期限)と納付の期限(納期限)が決められています。
そして相続税の申告期限と、相続税の納期限は同じ日になります。
その期限の日とは、被相続人が亡くなられた日の10か月後の同じ日となり、例えば1月15日に亡くなった場合は、その年の11月15日が期限となります。
法律上は少し違う書き方をされているのですが、多くの場合は上記の考え方となります。
なお、その期限の日が土日祝日等の場合は、その翌平日となりますので、例えば上記の例で11月15日が土曜であれば、翌平日である月曜日の11月17日が期限となります。ちなみに12月29日~1月3日は土日祝等に含まれることとなりますので、この間が期限の日となる場合はいずれも1月4日が期限の日となります。
4.納付の方法
相続税の納め方は何種類かありますが、もっとも一般的な方法は、現金による一括納付です。この場合の具体的な納付の手順としては、納める金額等を記載した納付書を金融機関の窓口に持っていき納付をするという形になります。
この際、税額分の現金を持っていくことも可能ですが、相続税ではその金額が多額になることが多いため、口座から直接払い込む方法を取る方が安全です。口座から直接払い込む場合には、税金分のお金を預けている金融機関の窓口に、前述の納付書に加え、通帳と金融機関届出印を持っていくことになります。これらを持参し、金融機関の窓口にて相続税の納付をしたいと伝え、窓口で渡される金融機関の所定の用紙にその場で記入・押印することで納付の手続きを行うことができます。
なお、この方法の場合は金融機関の窓口が利用できる必要がありますので、利用される金融機関の窓口の営業時間にはご注意ください。
5.まとめ
このように、税に関する手続きは複雑で、専門的な知識がなければわかりづらく、適切に手続きができなかったり、時には損をしてしまったりすることにもなりかねません。
当事務所では、税に関する手続きやコラム掲載にあたって、税に関する専門家である税理士と連携をとっております。相続手続についてご相談・ご依頼を受け、無事に相続手続きが完了してもそこで終わりではなく、その後相続した財産の運用や相続税についてどのようにしたらよいかを具体的に知りたいという場合は、税理士を交えてご意向をお伺いし、依頼者に安心していただけるような体制をとってまいります。